版画・写真表現の波紋
高松次郎・木下佳通代・彦坂尚嘉・木村秀樹・辰野登恵子・木村 浩・石原友明
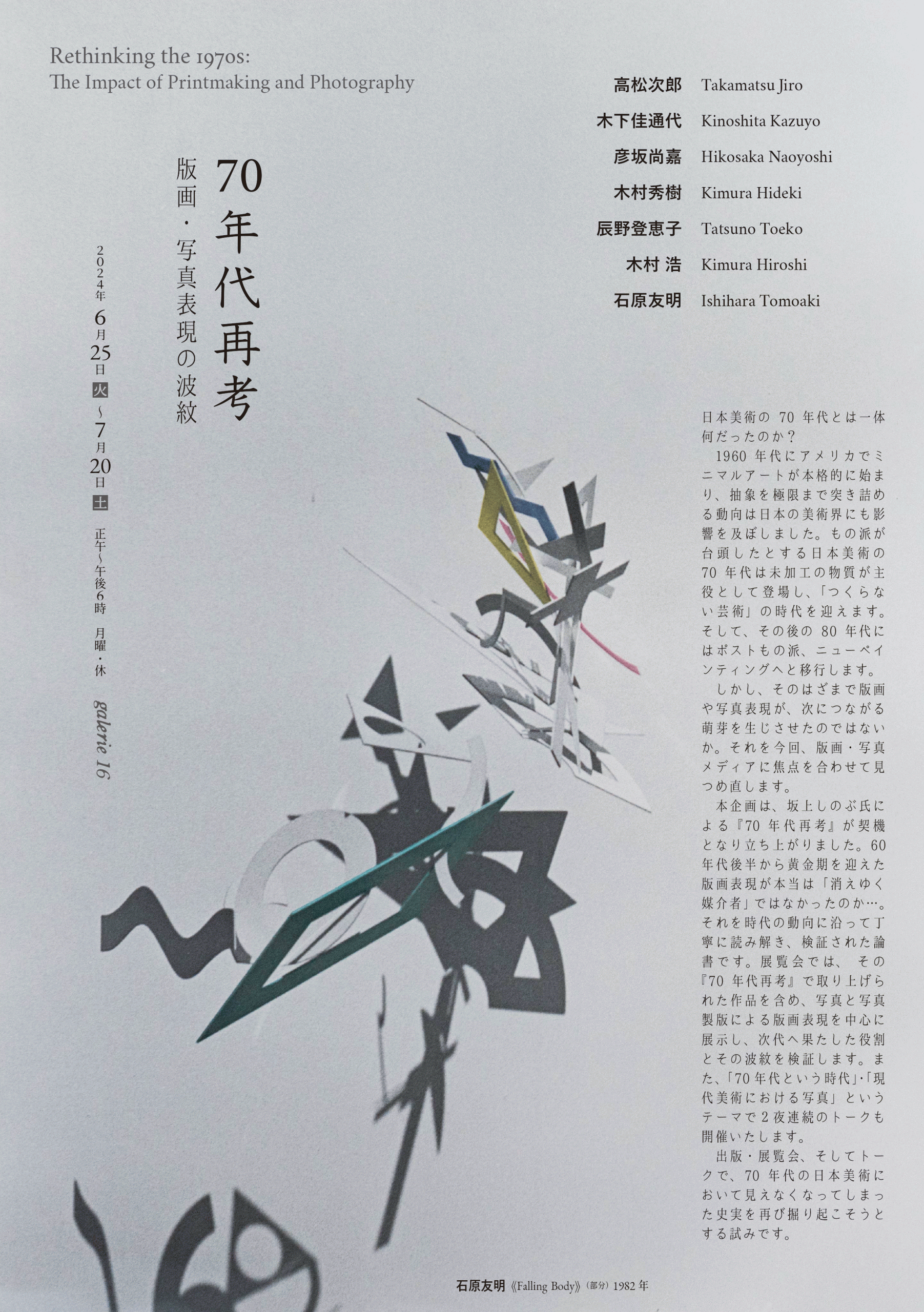
2024年6月25日(火)〜7月20日(土)
12:00〜18:00(月曜・休)
▶展示風景VRページでご覧いただけます!(新しいページで開きます)
▶アペルト会場の展示風景VRページでご覧いただけます!(新しいページで開きます)
■■ 坂上しのぶ著 『70年代再考』
▶︎ 再販(8/27・残りわずか)
———-
日本美術の70 年代とは一体何だったのか?
1960 年代にアメリカでミニマルアートが本格的に始まり、抽象を極限まで突き詰める動向は日本の美術界にも影響を及ぼしました。もの派が台頭したとする日本美術の70年代は未加工の物質が主役として登場し、「つくらない芸術」の時代を迎えます。そして、その後の80年代にはポストもの派、ニューペインティングへと移行していきます。しかし、そのはざまで版画や写真表現が、次につながる萌芽を生じさせたのではないか。それを今回、版画・写真メディアに焦点を合わせて見つめ直します。
本企画は、坂上しのぶ氏による『70年代再考』が契機となり立ち上がりました。60 年代後半から黄金期を迎えた版画表現が本当は「消えゆく媒介者」ではなかったのか…。それを時代の動向に沿って丁寧に読み解き、検証された論書です。展覧会では、 その『70年代再考』で取り上げられた作品を含め、写真と写真製版による版画表現を中心に展示し、次代へ果たした役割とその波紋を検証します。また、「70年代という時代」・「現代美術における写真」というテーマで2夜連続のトークも開催いたします。
出版・展覧会、そしてトークで、70年代の日本美術において見えなくなってしまった史実を再び掘り起こそうとする試みです。
———-
■トークナイト(定員30 名)
———-
●ファシリテーター:坂上しのぶ(美術史家)
第一夜:6月 28 日 ( 金) 18:00 ~ 20:00 「70 年代という時代」
ゲスト:中島一平(画家)/木村秀樹(画家/版画家)/長野五郎(美術家/染織研究者)
60 年代後半に世界規模で盛り上がったスチューデント パワーは、芸術大学にも大きな変革のうねりを巻き起こした。60 年代末に一学年違いで入学した3 人が経験した70 年代という時代。学生運動への情熱、敗北、虚無感、そして虚脱感。芸大に入ったものの、何かをつくりたいという気持ちはあるけども、何をやったらいいのか皆目わからない。つくらない芸術が唱えられた70 年代の制作現場、作家意識、時代状況……。3 人のトークが70 年代特有の精神を浮き彫りにする。
+
第二夜:6月 29 日 ( 土) 18:00 ~ 20:00 「現代美術における写真」
ゲスト:木村秀樹(画家/版画家)/木村 浩(美術家/情報デザイン)/石原友明(美術家)
ウォーホルのシルクスクリーン、ラウシェンバーグのリトグラフ等、版画は「現代美術における写真」の導入部分を担った手段である。写真を取り込んだ版画はポップ・アートを契機に普及し、70 年代初頭には、現代美術のメディアとして一般化した。“つくらない芸術” としての版画を見据えた木村秀樹、版画から出発して写真そのものを作品化した木村浩、写真表現の可能性を拡張し続ける石原友明。70 年代の現代美術の思考/志向が、3 人の写真史を通して明らかになる。
———-
■出版: 『70 年代再考』 著者:坂上しのぶ (発行:2024 年6 月中旬)
70 年代とは、いかなる時代だったのだろうか。
学生運動で騒然としていた熱き60 年代。一転して、無気力・無関心・無責任の「シラケ」時代と評される70 年代。「うしろめたさというメンタリティ」を抱えているのが70 年代作家だと語る版画家 木村秀樹へのインタヴューからはじまる本論は、版画を美術史上における「消えゆく媒介者」と位置付ける。
さらに筆者は、版画メディアを〈モガリ〉の役目を担った存在であるとして、〈影〉〈両義性〉をキーワードに、70 年代に版画が果たした役割の重要性を検証。版画が、「消えゆく媒介者」として隠されて(見えなくなって)しまった理由を、絵画の台頭、写真の台頭、ニューウェーヴの台頭の3 項にわけて論じ、80 年代美術に至るまでの、70 年代美術の思考を解き明かす。


